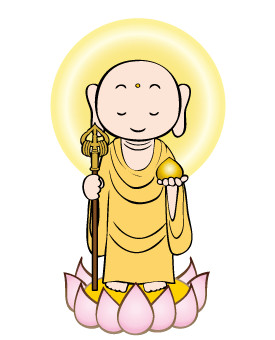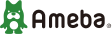「私と神様」第一章~第六章
「私と神様」 第一部
私と神様
~ 第一章 私の幼年期体験 お店のお客さん ~

私の田舎は熊本県のはずれにあって、四方を小高い山に囲まれたのどかな農村部です。
実家は、そんな集落で唯一、お店を営んでおりました。
食料品、お酒、タバコ、塩、農作業用品、歯ブラシから洗剤、靴下や雨靴まで、集落の人に必要と思われるもの全てを取り揃えていて、ちょうど今のコンビニエンスストアの原点とも思われるものでした。
夕刻になると村中から、おばさん達が集まって来て、井戸端会議が始まります。窓ガラスが震えるような、家が揺らぐような高らかな声が、お店の中に響きわたり、大変な賑わいでした。
私といえば、賑やかすぎるおばさん達の勢いに押され、両手で耳を押さえながら、たじろいでいたことを思い出します。
買い物を済ませたおばさん達がお店を後にすると、次は山仕事を終えた、おじさん達のご来店です。
当時は山林事業が最盛期の頃で、私の村の近隣の方達は、農業か林業で生計を立てておられました。
朝早くから山に入り、黙々と仕事をこなし、やっと長い一日が終わった家路の途中で、お店に立ち寄り、お互いの労をねぎらう事を日常とされておりました。
お店では、コップで焼酎のお湯割を出します。
おじさん達は、思い思いにお店に並ぶちくわやてんぷら、魚肉ソーセージなどをお酒のつまみにしながら、木製の丸椅子に座り、膝を突き合わせるように店内に陣取って、論議に花を咲かせます。
おじさん達の汚れた作業服が、あちらこちらと破れていたり、日焼けで赤いのか、飲み過ぎで赤いのか、やけにテカテカした艶の良い顔をしていたり、前歯が抜けて何となく間抜けな感じだけど、肩や腕は筋肉隆々で、いかにも「猛者」というような雰囲気を醸し出しておりました。
おじさんたちの話の内容は様々です。
ほぼ毎日集まって話をするのに、よくもこれだけの話題があるものだと、幼心に感心しながら聞いていたのを思い出します。
そんな話題の中で、時には「山の神様の祟り」にまつわる話や、山道の途中で「不思議な体験」をしたことなども話題に上っておりました。
最近では、そのような非現実的な話は嫌われる傾向にありますが、その頃は平然と、当たり前のように話題に上っていたものです。
そんな話があるときは、私も大人たちに交じって聞いておりました。
残念ながら、どんなお話だったかは覚えておりません。
ただ、今でもしっかり記憶にあることは、おじさん達の「目に見えないもの」への「感謝」と「気遣い」です。
おじさん達は、山の恵みが商いであり、生活の基盤であるのです。
もし、その恵みの山に何らかの理由で立ち入れなくなった時は、たちまち生活に困ってしまうのです。
ですから、山は自分の「命」と同様か、それ以上に大事なところなのです。
だからこそ、「気遣い」を忘れません。
山だけでなく、川や樹木や井戸などの生活の身近にある「自然界の造形物」を、まるで「人」のように捉え、「人」に対する気遣いで接するのです。
おじさん達は、山で安全に無事に仕事を行うために、山の神様の領域を穢したり荒らさないようにすることが大事であり、基本的なルール・マナーであって、それを侵すと、自身に災いが降りかかるということを信じていたのです。
「その恵みのお陰で、私たちは暮らしていくことができる・・・、だからこそ穢してはいけない、荒らしてはいけない・・・」と、常に考えていたのです。
まるで山が「人のように生きている・・・」と想像することで、山を敬い、自然を大事にすることが出来るのです。
そして、「今日も一日無事に仕事ができたのは、山の神様のおかげだ・・・」と、手を合わせ感謝するのです。
おじさん達は、自分なりの神様に対する「想い」をそれぞれに持っていて、その思いを皆で話し合いながら、神様へ手向ける心構えの共有を意識的に図っていたように思います。
それはまるで、「だれ一人も怪我することなく、みんなが共に、無事でがんばろうな・・・」と、声を掛け合って、助け合っているようにも思えました。
これもまた、厳しい自然界と共に生きるための「知恵」と「工夫」であったのでしょう。
私が今日、神様と向き合う気持ち、神仏をお奉りする心は、まちがいなくこのおじさん達の影響も受けたものだと思うのです。
私と神様
~ 第二章 私の幼年期体験 炭焼き窯の神様 ~
当時、私の田舎では、「炭焼き窯」を方々で見かけることができました。
「炭焼き窯」とは、粘土質の土に水を適度に加え、その土を上積みしながら固め形成したもので、窯の中は、大量の炭材を詰めるための空間が施され、煙が出るための煙突が設置されます。
窯には雨をしのげるような簡単な屋根が取りつけられます。
これらは「炭焼き小屋」と呼ばれます。
炭材の準備が整い、一旦窯に火が入ると、昼夜を問わずつきっきりで火の番をします。そうして数日後に出来上がった炭は、黒々として、叩くと「カラン・・・」と実に爽やかな音を奏でるのです。
どこの地域でも同じように、私の田舎でも「炭焼き窯」を「神聖なもの」として考えられていました。
ですから当時、「炭焼き窯におしっこをかけると局部が腫れるよ」と、よく大人たちに言い聞かされていたものです。
幼心にも、にわかに信じることのできない話ではありましたが、目に見えないものへの恐怖心も手伝ってか、大人の教えは忠実に守っておりました。
ですがある日、何故かいたずら心がムクムクと湧き上がり、あろうことか窯の頂上部分に向けておしっこをかけてしまったのです。
その直後は何事もなく、その後も普段どおりに近所の子供達と遊んでおりました。
「なんだ・・・やっぱりどうもないじゃないか・・・」
そういった思いを抱きつつ、その事すら忘れてしまった数日後の朝。
目が覚めると何やら下半身に違和感を覚えます。
おそるおそる下着をおろしてみると、なんと、局部が真っ赤に腫れあがっているではありませんか。
まるで、信楽焼きの「たぬき」そのものです。
まさかあの話が真実であったと身をもって体験することになろうとは!
私は泣きながら、慌てて母に訴えました。
さわぎを聞きつけた私の父は全く慌てる様子もなく、「ほっといても直る!」と言い放ち、出て行きました。
今にしてみれば父の言動は、非情のようにも感じられますが、しかし、父の言う通りでした。
2~3日後には、すっかり腫れも引いて、元通りになったのです。
しかしその間は家にこもり、下着を身に着けることもできないほど腫れて、熱が籠った局部を何とかしたくて、団扇でパタパタと扇いだり、氷水で冷やしたりと、ひたすら手当てに専念しておりました。
数年後に聞いた話によると、その時、冷たいことを申した父は、あれからすぐに私がおしっこをかけた炭焼き窯に向かい、コップ一杯のお酒と一升瓶をお供えして、許しをいただけるようにと手を合わせてくれていたのだそうです。
父は昔の人間で、無骨者ですが、父のとった行動は、父なりの愛情表現でありました。
大人になって初めて、父の事を「ありがたいものでかけがえのないもの・・・」と、思えるようになりました。
昔から「炭焼き窯」には「神様が宿る」と考えられており、私の田舎では荒神様のお札が炭焼き小屋に貼ってありました。
また、窯を所有する家でのお祝い事や、お正月などの特別な日には、必ず、炭焼き小屋にもお供え物があがっておりました。
生活に重要で、かつ、意味を持つそれらには、必ず神霊が宿り、その神霊のご加護の元に生きていけるということを、昔の人は知っていたのだと思います。
ただ単に「炭焼き窯を作れば自然と神様が宿る・・・」という理由ではありません。
「炭焼き窯」では長時間にわたり火が入りますから、「出火して火事にならないように・・・」という祈りと、当時は炭の価値が高かったことから「良い炭ができるように・・・」と願う気持ちが、「炭焼き窯」を「大事にせねばならぬ」という、「敬う」思いと「恐れ」という心情に発展して、信仰の対象になったものと考えられます。
だからこそ日本では古くから「八百万の神」という観念が根付いたのでしょう。
「物を大事にする・・・」という人々の精神は、とても神聖なものです。
その「精神にこそ神霊が宿る」と考えております。
ですからその、神聖な精神に対して不敬をしますと、その見返りとして、災いが襲ってくるのです。
そういった日本人古来の思想は、これからも大切にして、子孫にも語り継ぐべき重要な事だと考えております。
神仏を敬い大事にする・・・と、いうことは、いくら頭で考えても、具体的な理解には、なかなか至りにくいと思います。
だからこそ、親から子へ、子から孫へと、受け継がなければならないのです。
山仕事のおじさん達もまた、「山の神様を怒らせないように・・・と気遣いながら、それらの「目に見えない絶対的な存在」に対して、日頃から山に入る自分たちが不敬の所業を慎むことこそ、山の恵みをいただくための最低限のマナーだと考えていたのです。
それらは、決して理屈ではありません。
そうして代々受け継がれた精神であったのでしょう。
まさに、様々な経験を通して得た知識でありました。
そういった大人たちの姿や行いは、善きも悪しきも、次代の子供達に受け継がれるものです。
子供達は、神仏や自然に対して手を合わせる大人たちの姿を見ることで、真似るようになります。
それはきっと、目には見えない「心」と「心」の「ふれあい」を学ぶことになるのです。
子供たちは「心」を大事にすることを身につけることで、やがて人に対する「気遣い」や「思いやり」も持って、やさしく穏やかな人生をおくるようになるのです。
そうすると、きっとこの世の中から「争い」や「いがみ合い」、「戦争」などの無くなるのです。
心を思い、心に寄り添うための考え方こそが「信仰」というのです。
「信仰」とは、心を大事にして、心を尊重するための手段です。
今の時代に大きく欠落した私達の「基本的な信仰心」・・・。
忘れないようにしたいですね。
私と神様
~ 第三章 私の幼年期体験 土葬と火の玉 ~
昭和35年位まで、私の村でも「土葬」が行われていました。
私は、それよりも後期の生まれですから、実際目に触れることはありませんでしたが、母から聞いた話によると、土葬は決して気持ちの良いものではなかったと言います。
土葬は通常、死後硬直で固まった遺体を「座棺」という大きな桶(おけ)状の棺に、膝を抱えるように折り曲げて収め、墓場まで村人が総出で運んだそうです。
座棺には丸い蓋がかぶせられ、棺の上部に四角い柱が渡されて、その前後を村でも若手の男衆が担ぎます。
先頭は鐘を持ったお坊さんが、お経を唱えながら歩きます。
次に棺が続き、その後ろに位牌を持った喪主が立ち、造花を持った者、ご飯や団子などのお供え物を持った者、五色の旗を持った者、藁で編んだわらじを持った者など、遺族・親族・村人たちが続いて、墓場までの道のりを、行列になって練り歩きます。
墓場では、あらかじめ当番で決められた男衆が墓穴を掘って、棺が到着するのを待っています。
一行が到着すると、お坊さんの指示により、墓穴に棺が入ります。
母によると、思うように深くは掘ってなかった・・・といいます。
墓穴を見下ろすと、穴の中には白い骨が見えていることもあったそうで、既に先人が埋められている場所を掘り起こした・・・という事も、決してめずらしくはなかったのだそうです。
棺が墓穴に納まりますと、まず遺族が棺の上に素手ですくった土をかけるのですが、墓穴を掘った際に盛り上げられた土ですから、先人の、誰ともわからない骨片が紛れていたそうです。
一切の儀式が終わった後は、決して後ろを振り返ることなく、去らなければなりません。
振り返ると、死者に呼び込まれると、固く信じられていたようです。
葬式が終わると、夏場で数日、冬場で数週間のうちに「火の玉」が出没します。
現代では「火の玉」の正体が「遺体が腐敗するとき」に発生する「リン」という物質であることが確認されていますが、当時の人々は「火の玉=死者の魂」と考えていましたから、突然、火の玉を目撃した時は、想像を絶するパニック状態に、陥ったに違いありません。
「火の玉」というと夜間に墓場で目撃されるもの、というイメージですが、当時、村の上空をふわふわと飛んでいるのを見かけることは、珍しいことではなかったそうです。
そんな話を、母は平然と話しておりましたが、一度だけ怖い思いをしたことがあったそうです。
ある日のこと。
行き場を迷っているかのように、まるで「徘徊」しているかのように飛んでいた「火の玉」が、我が家の屋根の上で「すぅ・・・っ」と消えたことがあったそうです。
母は、「その時はさすがに肝をつぶした・・・」と申しておりました。
昔から、「家屋の屋根の上で火の玉が消えると、その家で近いうちに死人が出る」という言い伝えがあったものですから・・・。
ですが幸いなことに、我が家では、しばらく死人が出る事はありませんでした。
この一件について、しばらくは村中で、ひそひそと噂されていたそうです。
「中村さんちの誰かが、近々死ぬ…」って…。
私と神様
~ 第四章 私の幼年期体験 隣のおじいさん ~
あれは私が3・4才のころだったと思います。
私の実家の前は車道が通っており、車道を挟んできれいな小川が流れています。
その小川を渡ってしばらく歩くと、老夫婦が住まう家がありました。
その老夫婦は自他共に認めるおしどり夫婦で、私のこともよく可愛がってくれました。
私も、気さくで、とてもやさしいその夫婦のことが大好きで、暇さえあれば遊びに行っておりました。
遊びに行ったとき、一度、びっくりする光景を目の当たりにしたことがあります。
それは、ある暑い夏の日の日暮れ時、おじいさんが縁側で爪を切っていたのですが、その切り方が、とてもショッキングで、今でも脳裏から離れません。
縁側に腰を下ろし、片足の膝を折り、背中を丸めて前かがみになり、足の爪を切っているまでは普通の光景でしたが、なんと手には、「爪切り」ではなく「剪定ばさみ」を持っているのではありませんか。
それを器用に使って切っているのです。パチン、パチンと、とても上手い具合に、ま~るく…。
さすがに私もびっくりして、「痛くないの?」と、たずねた程です。
しかし、おじいさんはいつものように、何も言わず、ニコニコしながら、いかにも固そうな足の爪を、上手に切っていました。
そんなおじいさんも、年のせいでしょう。
たびたび体調を崩して、入退院を繰り返していました。
ある日、退院してきたおじいさんと、久しぶりに遭遇したのです。
私は小川で遊んでおり、おじいさんは、川上にある自宅から自転車を押しながら下ってきました。
その小川に架かる小さな橋の上で、私はおじいさんとすれ違ったのですが、何だか、いつもと勝手が違います。
あきらかに、おじいさんの「存在感」を感じられないのです。
それはまるで、おじいさんがこの世の人ではないような、そんな感じがしてしまったのです。
私は「良からぬモノ」でも見たような気がして、驚きと恐怖感に、戸惑いを覚えました。
その時はまだ幼い私。
その意味が理解できるはずがありません。
今、当時のおじいさんの様子を思い返しますと、俗にいう「影が薄い・・・」という言葉そのままに、生気が抜けてしまった状態であったと思われます。
だからでしょうか、その時は、おじいさんがとても小さく見えました。
そして肌の色が、真っ白というよりも、まるで「無色透明」といいますか・・・、おじいさんの体を通して、後ろの背景も透けて見えるような感じです。
いつもと違う、ただならぬ雰囲気に、私は無言で、食い入るように、おじいさんを見つめておりました。
それから数日のちに、緊急入院したおじいさんは、帰らぬ人となりました。
私と神様
~ 第五章 私の幼年期体験 村の地蔵堂 ~
私の村に、地蔵堂があります。
小さな地蔵堂ですが、あたりに民家はなく、少々騒いでも怒られない、子供にはかっこうの遊び場でした。
秋になると境内にある「しいの実」がたわわに実って、落ちた実を拾っては母にねだって、フライパンで炒ってもらい、おいしくいただいておりました。
その地蔵堂におられるお地蔵様は、なぜか“赤い顔”、“赤い体”をしておられます。
子供の頃はこのお地蔵様がとても怖くて仕方ありませんでした。
幼心に、このお地蔵様の赤い色がまるで、「赤鬼」のように思えたのです。そして「血」を、にわかに連想しておりました。
とにかく怖くて恐ろしくて・・・。
お地蔵様をまともに見上げることができなかったことを覚えております。
ですが母は、「あのお地蔵様はとても子供が大好きな仏様だから、あなたはお地蔵様のためにも、あそこで遊んであげてね」と申します。
あんなに怖い仏様なのに・・・。
なぜ母は「子供が好きな仏様」などと言うのか・・・。
幼い私には、母の言葉が理解できませんでした。
それでも私は、そんな母の言葉に心惹かれ、なるべく仏様の顔を見ないようにしながら、常に、怖いお地蔵様の気配を感じつつ、遊んでおりました。
今から思っても、当時の幼い私には、この地蔵堂の前で遊ぶのは、結構、ストレスのかかる時間であったようです。
年を重ね、自分の子供が産れたとき、ふと幼かった時の思い出と、その地蔵堂に関わる母の言葉を思い出しました。
そこで、帰郷した折に、子供たちを連れて詣でることにしたのです。
しかし、当時の恐怖心が消えたわけではなかったようで、大人の私にとっても、それは一大決心でありました・・・。
実家から、子供たちと一緒に歩いても、片道20分とかかりません。
久しぶりに詣でた地蔵堂は、古かったお堂が建て直してあって、見違えるほどの、立派な建物に変わっておりました。
私は子供たちとお堂の前に座り、恐る恐るお地蔵様を見上げました。
お地蔵様は何も変わらず、昔のままの“赤い顔”、“赤い体”のお姿でした。
「・・・・・・。」
私は深いため息をつき、まるで心身の緊張の糸がぷつん・・・と切れたような、そんな脱力感に襲われました。
「あー、なぜあの当時は、怖くて仕方なかったのだろう・・・。
こんなに安らぎに満ちた、おやさしいお顔なのに・・・」
あんなに怖くてまともに見ることができなかったお地蔵様のお顔を、大人になった今、ようやく、しっかりと拝見することができました。
当時は、あんなにたくさんここで遊んでいたのに、産まれて初めて直視したそのお顔は、とてもにこやかで、体全体から「慈愛」の念がにじみ出ているのです。
「あ―、どうしてこんなにやさしい仏様を、まともに見ることができなかったのだろう…」
私は、なんとも言えない気持ちで、しばらくの間、子供たちと共に魅入っておりました。
お地蔵様を見つめているうちに、当時が思い出され、母の、あの言葉が脳裏に浮かび上がります。
「子供が大好きな仏様だから、あなたは、あそこで、遊んであげてね・・・」
私は、この言葉を、我が子に、母と同じように告げました。
「この仏様は、この村で生まれた全ての子供の守り神だから、きっと、おまえ達のことも守ってくださるよ。よーく、お参りして帰ろうね・・・」
私の言葉を耳にした子供たちは、神妙な面持ちで、お地蔵様に手を合わせておりました。
私は、そんな子供たちが大変ほほえましく、幼いころに母から聞いた言葉を、今度は親となった私が、幼い我が子に伝えられたことを、大変うれしく思いました。
そうして、「縁」の不思議さと奥深さを感じて、例えようのない感動を噛みしめておりました。
大人になった私の目の前に、幼いころと変わらずいらっしゃる、お地蔵様のお姿を目の前にしながら、とてもありがたい思いに浸りました。
私自身、やさしく、慈しみに満ちあふれた人になれたような気がしました。
そんなひと時を過ごしました。
それから十数年経った今、「審神者」としての職にある私が、改めて審神者術を施したところ、この一連の思い出には、実は、私の前世と、今世の母との「縁」について、とても深い意味があったことを知ることになりました。
なぜ、母は私に、このお地蔵様のところで遊べと言ったのか・・・。
そしてなぜ、幼いころの私が意味もなく、この赤い顔のお地蔵様を、あれほど怖がっていたのか・・・。
そのことに秘められた、私の前世に関する、ある重大な因縁がわかったのです。
それはまた、いずれの機会に・・・。
私と神様
~ 第六章 私の幼年期体験 私の家族 良縁に恵まれる条件とは ~
私の母は、いくらばかりの「霊感」はあったようで、病人の身体などを、手の平でさすりながら、お経を唱え、病状を和らげるようなことを行っておりました。
幼いころから病弱だった私も、母の手にかかると、身体がとても楽になったことを記憶しています。
しかし、母もまた霊媒体質であったが為に、そんな行為から、相手の悪いモノを吸い取っていたようです。
吸い取ってもらった方は、母に、「悪いもの」が移ったわけですから、症状は改善します。
逆に、吸い取った方の母は、辛い目に逢うのです。
これは、「手かざし系」教団が行う、「手かざしの術」と同じ仕組みです。
「手かざしの術」とは、相手の患部に手をかざすことで、高次元のエネルギーを放出して、体調を良くしてあげよう・・・とするものですが、実は、かざした手の平から、エネルギーが放出されるのではなく、手をかざすことで、相手の「悪因縁」を吸い取っているのです。
「悪因縁」を吸い取ってもらった人は、一時的にも体調が改善したように思えますが、しかしそれは、あくまでも「一時的」なことですから、しばらくするとまた、その人の元に戻ってきてしまいます。
「浄霊は、本当は難しいことだけど、ここの神様は特別な神様で、特別に選ばれた人だけに奇跡を施してくださるのだ!この“教え”を学ぶ人だけに、特別な神様が、特別に、浄霊の業を与えてくださるのだ!」
そんな教えの下で、一生懸命、人助けや自分の為に、「手かざしの術」が実践されますが、「手かざしの術」の実践を繰り返せば繰り返すほど、他人や土地などに憑依する「悪因縁」を吸い取っていくのです。
手かざしの行為をやればやるほど、施術者の身体が蝕まれ、心も安らぎを失い、本人だけでなく、家族の「運気」まで落ちていくのです。
長くやればやるほど、抜け出せない、悩みの負の連鎖に陥ってしまいます。
いつの時代も、そうそう簡単に、人の抱える「悪因縁」を解くことはできません。
本当に、手の平から高次元のエネルギーを放出して、人様を救いたい・・・と思うならば、高次元の神様のご指導の下で行う、それ相応の「修行」が必要なのです。
しかし、それは何も「手かざし系教団」に限ったことではありません。
「奇跡」を詠う、ほとんどの個人から団体までが、「苦労もなく、あっという間に奇跡が起こる!」、「自分の崇拝する神様が、人間の為に、奇跡を起こしてくださる!」などとと言います。
そんなフレーズで信者集めをする者は、人の抱える「因縁」を軽んじたり、誤解しております。
簡単には消すことの出来ない、難しくて広大で、なおかつ、人智をはるかに超える「悪因縁の仕組み」を、まったく理解しておりません。
人々に関わる「悪因縁の仕組み」や「質」を理解していないところで行う「霊術」は、大変危険な行為です。
目に見えない因縁は、「浄めてはいけない因縁」や、「動かしてはいけないもの」がほとんどなのです。
「悪因縁」を無理矢理扱うことが、どこに、どんな形で、周りに波及するか、見当もつきません。
「因縁」とは、とてもデリケートであり、また広大で深遠なものなのです。
一筋縄では、まいりません。
ですから、それらは大変、危険極まりない・・・と、言わざるを得ません。
また、みなさまが実際に、病状や状態が改善した人の「奇跡体験談」などを聞かれたとしても、そのほとんどが「まやかし」か「気休め」、「思い込み」だと考えます。
さて、前出の母は、そんな「因縁の仕組み」に気がついていたのでしょうか…。
そんな行為を行った日の夜は、決まって長時間にわたり、必死で仏壇に向かい、読経しておりました。
今思うと、一心に行っていたその術で、吸い取った相手の邪気を、自分の身から振り祓い、浄めていたのかもしれません。
しかし母が行っていた、その祓いや浄めの術は、上手くできていなかったように思います。
自分の身にもらった(移った)「悪因縁」を晴らす術が、満足ではなかったからこそ、母の半生は、波乱万丈であったのです。
病気に苦しむ母の姿は、とても哀れなものでした・・・。
ですから、私は母を慕い敬う一方で、「母のようにはなりたくない…」という思いを、強く秘めていたのです。
母の半生を見て、「母の人生は良くない・・・」と考える度に、あれだけ一生懸命に神仏の信仰をしていた母が、「なぜ不幸だったのか・・・」と考えてしまいます。
ですからきっと、神仏や信仰を、一切、否定して生きるならば、私は、母と同じ運命をたどることはないのだと、考えました。
しかし、頭でそう考えたとしても、結局私は、神仏を否定する生き方はできなかったのです。
かつて母は、こう申しておりました。
「神仏は私の命だから・・・」
そんな母の言葉を当時の私は理解できませんでしたが、神仏におすがりしなくては生きていけないような様々な経験を通して、神仏を否定して生きていくことなどできない、という事を、この歳になって思い知らされることになるのです。
神仏のご加護を深く実感した私の年齢は、奇しくも、母がひたすら仏様にすがっていた年齢と同じ頃でした・・・。
母の血をしっかり受け継いだ私は、やはり、母と同じ運命を辿って生きていかなければならなかったのです。
よく、神結神社にいらっしゃる方から聞かれます。
「霊能力という力は、遺伝するのでしょうか?」
確かに、広い意味での「血筋(遺伝)」というものになるのかもしれません。
しかし、私の場合は、前出のような、幼少期からの様々な体験により、「神仏の存在」を疑うことができない環境の中で育ってきたのです。
そこには、神仏を否定するような経験や生き方は、一切ありませんでした。
大好きだった今は亡き母の、言葉や行動に、大きな影響を受けていることに間違いはありません。
しかし、私が実感するところでは「霊能力は血筋(遺伝)・・・」ということよりも、むしろ「どのような環境に身を置いてきたか・・・」という「経験」が、大事な要素のように思えます。
そして更には「感性」という、すなわち「持って生まれた感覚(様々な出来事の意味を、理屈を超えたところの心で捉えること)」が、それを決めるものと、考えております。
「霊能」とは、目に見えない「心」を判断する能力のことで、目に見えるものや、耳から聞こえるもの、肌身で感じるものから、その「裏側」にある「心情」を読み取る「感性」のことを「霊能力」というのです。
私の場合は、それは生来より、自然と身についていた感覚であったと考えております。
ですから「霊能」という感性は、人が持ち合わせる「眼・耳・鼻・舌・身」という「五感」から受け取る情報から、「六根」と言われる「感情の分野」、すなわち「第六感的な感覚」で、どのように受取り、解釈できるかが、大事になるのです。
実は、その「六根」という、五感の奥の深いところにある感性は、人が、幾度も生まれ変わる「輪廻転生」のなかで、鍛え上げられるものなのです。
幾度も幾度も生まれ変わる中で、「感性を磨く」という課題に、何度も何度も取り組んできた経験と努力が、磨かれた「感性」となって現れるものですから、「血筋(遺伝)」というものとは異なるのです。
前世、前々世、、、と、度々生まれ変わる毎に、あらゆる生き物の「心」に焦点をあてて、それを知る努力を重ねてきた者が、本当の「霊能力」を得て、霊能を発揮するものと、考えます。
例えば、そのパフォーマンスで感動を与える、ミュージシャンも、役者も、スポーツマンも。美しい作品を生み出して感動を与える芸術家も。人々に愛情をもって接することのできる教育者も、社会のために働く政治家も。それぞれの職業に相応しい「能力」というものは、幾度となく行われる「輪廻転生」の中で、幾度も幾度も繰り返し取り組んできた「魂の経験」から、徐々に培われて開花する才能なのです。
人間が持つこれらの能力は、「輪廻転生」のなかで、積み上げ鍛えられてきた「感性」であるのです。
今世の私は、今の両親の子供として生まれてきました。
子供の頃から、神仏を疑う余地など、まったく無い環境に、身を置くことができたことは、本当に幸せなことでした。
そういった、今世の「出会い」もまた、自分自身の「感性」を発揮できるために、とても大事な要素なのです。
これを「縁」と言います。
その「縁」はまた、私の現在の家族とも、深く結ばれました。
その家族の「縁」が、私の「命」を救ってくれたのです。
過去に、こんなことがありました。
それは、私の娘が2歳の頃でした。
当時単身赴任をしていた私は、人生上で大きな失敗を犯し、そのことが世間に露見してしまいました。
生きる希望を見失った私は、すっかり荒んだ心の状態に陥ってしまったのです。
生きることが辛くなり、自信喪失に陥った私は、「自殺」をしようと思い立ち、当時の単身赴任先で、手首を切って死のうと、考えました。
そうして、ある日の休日、私は、死ぬ為の準備をはじめました。
まずは部屋の掃除からはじめ、荷物の整理をしました。
次に、お風呂のお湯を、浴槽いっぱいに溜めました。
そして、手首を切るための包丁に、洗剤をつけて、じゃぶじゃぶと何度も何度も、納得のいくまで洗いました。
包丁を洗いつつ、ギラギラ光る包丁を見つめては、その鈍い光に陶酔しました。
その時の様子はきっと、鬼気迫るものだったに違いありません。
最後の最後に、妻と両親に宛てて「遺書」を書きました。
失敗が露見してから、悶々と物思いにふける時間が長くありましたが、その時だけは、泣きました。
ひたすら、泣きました・・・。
とめどなく、次から次へと、涙が溢れ出ます。
そんなときって、不思議です。
まったく、「声が出ない」のです。
ただ黙って、涙だけが、とめどなく流れるのです。
涙で濡れてしまった遺書の書面を、タオルでふき取って、妻と両親のあて名を書きました。
そしていよいよ、包丁を片手に持って、お湯がたっぷり入った浴槽の前に立ちました。
もう、そこに一点の迷いもありませんでした。
左腕を湯船に入れて、右手で握った包丁を突き付けた、その時です。
リーン・・・。リーン・・・。
携帯電話が鳴りました・・・。
私の記憶では、確かに、携帯の電源を切っておいたはずなのに・・・。
私は、何かにつき動かされるように握っていた包丁を手放し、衝動的に、フラフラと、電話に出てしまったのです。
「もしもし~、パパ?」
電話をしてきたのは、2歳になる我が娘でした。
いつもは、妻がかけてきて、そのあと子供達に代わるパターンでしたが、このときは娘が生まれて初めて、最初から話をしてきたのです。
「何してるの~?パパ~?」
たどたどしく、かわいらしい声で話す娘の声が、電話を通してなぜか胸に響きます。
「え?えっと・・・今?・・・そう・・・だね、おうちのお掃除をしていたところだよ・・・」
まさか、「今ね、死のうとしていたんだよ・・・」などと、口が裂けても言えるはずもなく・・・。
まるで2歳の娘や妻に、今の行動を見透かされているように思えて、ひどく戸惑ってしまいました。
まさか、このタイミングで電話をかけてくるとは!
もちろん、遠くに住む家族に、私の様子が見えていたわけではありません。
妻にも一切、私のしでかした失敗を話してはおりませんでしたので、現状を知る由もありません。
私はその娘の電話で「我」を取り戻しました。
「あぁ・・・そうだった。やっぱり死んではいけないんだよな・・・」
死のうとしていた私は、まるで「悲劇の主人公」でも気取っているように、私の「死」によって、皆に少しでも自責の念を抱かせることができたなら、私の死は必ず報われる!などと、自分勝手で稚拙な考えに囚われていたのです。
私の死によって、本当に悲しむ人がいることを、考えることもできないくらいに・・・。
あの時、もし、このタイミングで、携帯電話が鳴らなかったら、今、ここで、こうして生きてはいません。
今も元気に生きていられるのは、家族の支えがあるからです。
まさに、「縁」の賜物です。
そしてこれこそが、神様より賜った「奇跡」でありまして、ありがたい仕組みであったのです。
この「妙」ともいえるタイミングで、私は救われました。
現世の両親の子として産まれてきたこと。
そして、かけがえのない妻との出会いと、結婚。
後に、息子が生まれ、娘が生まれ・・・。
私は、「この素晴らしい家族の“縁”を導いてくださったのは、間違いなく神様だ・・・」と、この時、深く悟りました。
そして、この世に産まれ出たことを、何よりもありがたく思い、これこそが「奇跡」と呼べるものだと、胸に深く刻むことができたのです。
そうして初めて、私は「私の生命」に対して、手を合わせて祈ることができたのです。
繋がる命、支える命・・・。
そして、「生きること」で、私を守り、導いてくださる存在と・・・。
まことに「縁」とは、とても不思議でありがたいものです。
この経験を通じて、私たちは決して「ひとりで生きていけない」ということを、悟ることができました。
人の世は、まことに苦しく難しいことばかりです。
しかし、自分自身の命を大事にすること、家族の「縁」に感謝し、人を大事にすること、それこそが、この世の唯一の「信仰」と考えて、それを実行することで、この厳しい世の中を生きていくことができるのです。
この世の、唯一にして真の信仰と言えるのは、「自分の生命を大事にする」ということです。それを基本にして「縁」でつながる「他の生命」と共に、どのように繋がり、どのように支え、どのように支えられるのか、ということを教えるものが「宗教」であり、これに学び、実践する姿勢を「信仰」というのです。
自分の命や家族の命を軽んじる者が、いくら祝詞や念仏を唱えようとも、御利益だのパワースポットだのといっては神社仏閣に参詣しようとも、自己啓発にと各種メディアを読みあさろうとも、幸せになることはできません。
最も大切な「命」を敬い、大事にできなければ、「信仰」とは言えないのです。
なぜならば、「命」は「神様」そのものであるからです。
私たちの「命」は、神様よりいただいた「唯一無二」にものです。
いわば、私たちの命は、「神様の分身」なのです。
「神様」である私たちの「命」を、この世で最も大事にすべきなのです。
「命は自分の物だからどうなろうが自分の勝手だろ・・・」と、言う人がいます。
そんな意識で生きていると、そのうち「生気」が落ちてしまいます。
自分の命を軽んじる人は、他人の命も軽く扱おうとします。
「命を大事にしたい・・・」
そう思う人は、自分の命も、他人の命も「大事にしたい・・・」と思えるのです。
世の中は「因果応報」の仕組みで成り立ちます。
「大事」と思えば大事にされます。
「どうでもよい」と思えば、「どうでもよい扱い」を受けてしまうのです。
これは自分自身の「運」を決める大事な要素です。
日頃の「自分の命」への考え方や向き合い方によって、「良い運気」と「悪い運気」が決定するのです。
例え、「開運」をあやかろうと、足しげく有名なパワースポットに出かけたとしても、「自分の命」にきちんと向き合って大事にする努力を積まなければ、決して「開運」には至りません。
ここの神様は〇〇の効果がある・・・などと言う情報に振り回されるような「ご利益信仰」は、最も大事にしなければならないものから、目を背けさせることにもなります。
このような、人々が安易にご利益だけを追うように誘導する、現代の宗教界は、その考え方や在り方を改めねばなりません。
私たちにとって、この社会で生きていくために、一番大事なことは「良縁」という、人と人との間柄です。
この世は、ひとりで生きては行けません。
必ず、だれかと関わって生きて行かねばなりません。
その、「自分に関わる人の縁」は、自分にとって「良いもの」でなければ、苦難・苦境に至るばかりです。
「良い運」とは、これから先に起こる出来事や、出会う人が、自分にとって「良いもの」である、ということです。
自分にとって、悪い出来事や悪い人との出会いを「悪縁」といい、良い出来事や良い人との出会いを「良縁」というのです。
これから先の、未来に起こる出来事を、良いものにして、人間関係を良縁で結びたい・・・と思うのなら、まずは「自分の命を大事にすること」が良縁成就の鍵なのです。
私は、大事な家族の「縁」により、この「命」を助けてもらいました。
妻と子供たちと、とても良い、大事な「縁」を結んでいただきました。
この大事な家族の「縁」を導いてくれたのは、私の父と母、そして妻の父と母です。
そして、自然豊かで素朴な環境の中にあった、のどかな村の環境です。
更に、忘れていけないのは、村のお地蔵様や土地の神々とのご縁です。
「縁」は「命」でつながれ、「命」は「縁」で守られるのです。
大倭神道のご導神は、このようにおっしゃいました。
「自分の命と、あなたが大事とする者の命を、この世で最も大事にすべきもの・・・と、思いなさい。
縁でつながるすべてのものは、良いことも悪いことも、すべて、あなたと共有するものですからね・・・。
いいですか。
これは心に刻みなさい。
敬い、拝むべきは「命」ですよ。
そうでなければ「良い縁」は結ばれません。
一番、大事なことを疎かにしては、幸せにはなれませんよ・・・」
この、神様のお言葉を実行すれば、運氣が良くなり、これから生きる未来に、例え辛いこと苦しいことがあろうとも、乗り越えていける為の力が沸いてくる、ということです。
困難を制する力のことを「生命力」と言います。
「生命力」にあふれていると、次第に、悪い事柄や悪い者は、自然と近づいて来なくなるものです。
これを「良運」と言い、「良縁」に恵まれるきっかけになるのです。
なかなか良い人と出会えない・・・と嘆いているみなさまは、自分自身の言動や潜在意識が、後ろ向きになり、悪い気を放っていることに、気づかねばなりません。
「良縁」とは「幸福感」から出るものです。
「幸福感」を得るためには、現世での努力とともに、命を産み育んでくださる「命の神」へ感謝の念を持つこと・・・が大事なのです。